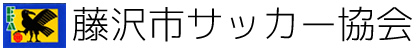=資 料=
12/31 藤沢市少年サッカーリーグ2023の記録
・3年生以下の結果
・6年、5年、4年生の結果
10/15・公営3球技場の使用状況
9/22・公営3球技場の使用状況 訂正版
9/21・公営3球技場の使用状況
9/9 ・第56回藤沢市少年サッカーリーグ 後期ブロック表
12/31 無事に終わりました
変則的になった今年のリーグ戦でしたが、無事に全ての日程を終えることが出来ました。『コロナ感染症』が弱まり、3年半ぶりに、声を出しての応援もできるようになり、スポーツの観戦やイベントの参加も、また、思いっきり楽しむことが出来るようになりました。
後期リーグ戦の結果がまとまりましたので、ご覧ください。
会場提供をしてくださったチームのみなさん!色々とありがとうございました。みなさんのおかげで、大会は無事終了いたしました。
12/9 大庭スポーツ広場球技場 3年生下位ブロック
秋葉台球技場で行われている『県選抜少年サッカー大会』に向かう途中、『大庭スポーツ広場球技場』を見たら子どもの姿が目に入りました。『リーグ戦』?確か午後からじゃ・・・・?と、向かったら、3年生たちの元気な声が聞こえてきました。
Bコートでは、指導者の方体がコートづくり。先々週の『藤沢招待』のラインが薄く残っていたようです。コートづくり、ありがとうございます。
3年生チームのみなさん、指導者のみなさん、そしてお母さんにお父さん、おばあちゃんにおじいちゃんも、みなさんが楽しそうでした。
そんな風景をを見せてもらえた私も、なんだか楽しくなってきました。







会場で指導者の方たちと立ち話をしました。
・3年生下位ブロック9チームの大会運営について・・・チーム数が多い分、試合日程が増え、1日に2会場でリーグ戦を行う。会場探しが難しかった。結局は『大庭スポーツ広場球技場』を多く使い、朝からの実施や2面使ってリーグ戦を行った。
・団員の人数・・・今回はインフルエンザの流行もあり、試合人数がギリギリの8人!になってしまい、怪我をしないように願っている。逆に後期に増え、初めてボールを蹴る子たちもいて、教え方が難しい。など、真逆の悩み事もありました。
・試合開始時の人数の8人・・・再考の希望が出るのでしょうか?
ポカポカ陽気の大庭グランドは、試合会場兼弟妹たちの芝生広場になっていました。走ってどっかに行ってしまうちびちゃんたちを追いかけるパパパママたち!いろんな声が聞こえてきました。
11/19 昨日は風が、半端なく凄かった!
本当に朝晩は寒くなって・・・。もう、暖房のお世話になっています。
18日は2会場にお邪魔しました。八松小会場は2年生、鵠洋小会場は6年生でした。合わせて3試合、それぞれ20分~30分ずつ見せてもらいました。久しぶりの学年差の観戦で、小学生年代の成長(体に、技術と戦術)を目の当たりにし、改めて環境を整えることの大切さを考えさせられました。
八松小で指導者と話をしました。コートの横が短く(40Ⅿ弱)、中々会場提供が出来なかったとの話。3年生以下の会場で構いませんから、これからも会場提供をお願いします<m(__)m>
八松小会場は、保護者も指導者もホンワカ!風は冷たいのですが、心はポカポカしました!ハーフタイムに監督が話していると隣の子が『つんつん…。』と、指先で一生懸命に監督を突っついて・・・、思わず笑ってしまいました。この子たちがあと何か月かすると全く変わった表情を見せてくれると思うと、ちょっと感慨深いですよね!




6年生は展開が速く、8人制のコートサイズでは少し狭いのかな?と思える場面もありましたが、個が場面に応じて考える(パスの受け方、パスを出した後のポジションの取り方、そしてお互いに声を掛け合って微調整する)、スペースの使い方などにチームの特色も出ていて、楽しく見せてもらいました。先日、BSでオフトさんが横浜のA中学のサッカー部に指導するドキュメントを見ました。時間は遡りましたが、待つこととヒント、タイミングが難しい。







9/22 公営球技場の使用状況 を訂正します
11/11(土)
大庭スポーツ広場球技場 Aコート 藤沢招待・・・9時~15時
Bコート 午前:指導者講習会 午後:使用可(12時~15時)
女坂スポーツ広場球技場 午前:藤沢選抜U12 午後:6年下位①
となります。
10/15 公営球技場を使いませんか?
後期リーグ戦の開幕を1週間後に控え(ブロックによっては既にスタート)、各チームの練習も熱を帯びてきていることと思います。
小学校ではインフルエンザが流行っているようです。秋は行事が多く、体力面での心配が低学年の子どもたちにはあります。
『公営球技場の使用状況表』を更新しました。
✖印 = 利用はできません
ー印 = 利用できます
*10/28・・・大庭スポ広.と女坂スポ広.両球技場ともに全日の空きとなっています。
ご覧頂けば分かりますが、既に、会場多くの時間枠を、みなさんに使っていただいています。ありがとうございます。
大会のために確保した会場(コートづくりは必要ですが・・・)ですから、どんどん使ってください!
利用しない場合は、他の団体に使っていただくためにキャンセルをします。
9/21 公営球技場の使用状況
各ブロックの会場担当のみなさん!会場調整と日程調整!色々とありがとうございます。
リーグ戦中の公営球技場利用状況一覧を載せました。
藤沢招待の初日(11/11)1会場が足りないために、大庭スポーツ広場球技場の片面を終日使うことになります。
公営球技場の空いてい時間帯は、是非!リーグ戦でお使いください。
9/9 『2023後期リーグ戦』のブロックが決まりました
9/7(木)に開いた『第4回少年委員会』で、後期リーグ戦の詳細が決まりました。
前期リーグ戦は、1ブロックのチーム数を増やし、1節2会場を使っての大会運営を基本に実施しました。7月の『少年委員会』では、今回変更して行なったリーグ戦について、多くのご意見や感想をいただきました。(調整、お疲れさまでした!)
その後、それぞれのサッカー団で『新しく行った運営方法について話し合い』、アンケートに答えていただきました。
今回は、このアンケートを受けての提案となりました。
リーグ戦のブロック分けの前に、
出席した指導者の方たちから、次のようなご意見を頂きました。
・少年サッカーを指導する熱い気持ちと、
・これから先の協会運営にもかかわる心配(このままの増え方だと、会場不足で大会が行えなくなってしまう等)、そして、
・学校会場を提供しているが、10年来、同じようなお願いを続けている。これは、どういうことなのか?
指導者ももっとお手伝いをするので、
・検討事項など、一緒に考えていい知恵を出しましょう! 『小委員会』方式などは?などなど
複雑な胸の内のお話と、前向きな提案を頂きました。
⚽が好きな子どもたちが、楽しんでボールを蹴ることが出来る環境をつくり、
同じように⚽好きな、そしてお子さんにつられて好きになろうとするお母さんとお父さんや大人たちが、みんなで一緒に楽しめる環境を 提供したいと思います。
頂いたご意見を役員一同で共有し、お答えしていきたいと思います。(文責 金田)